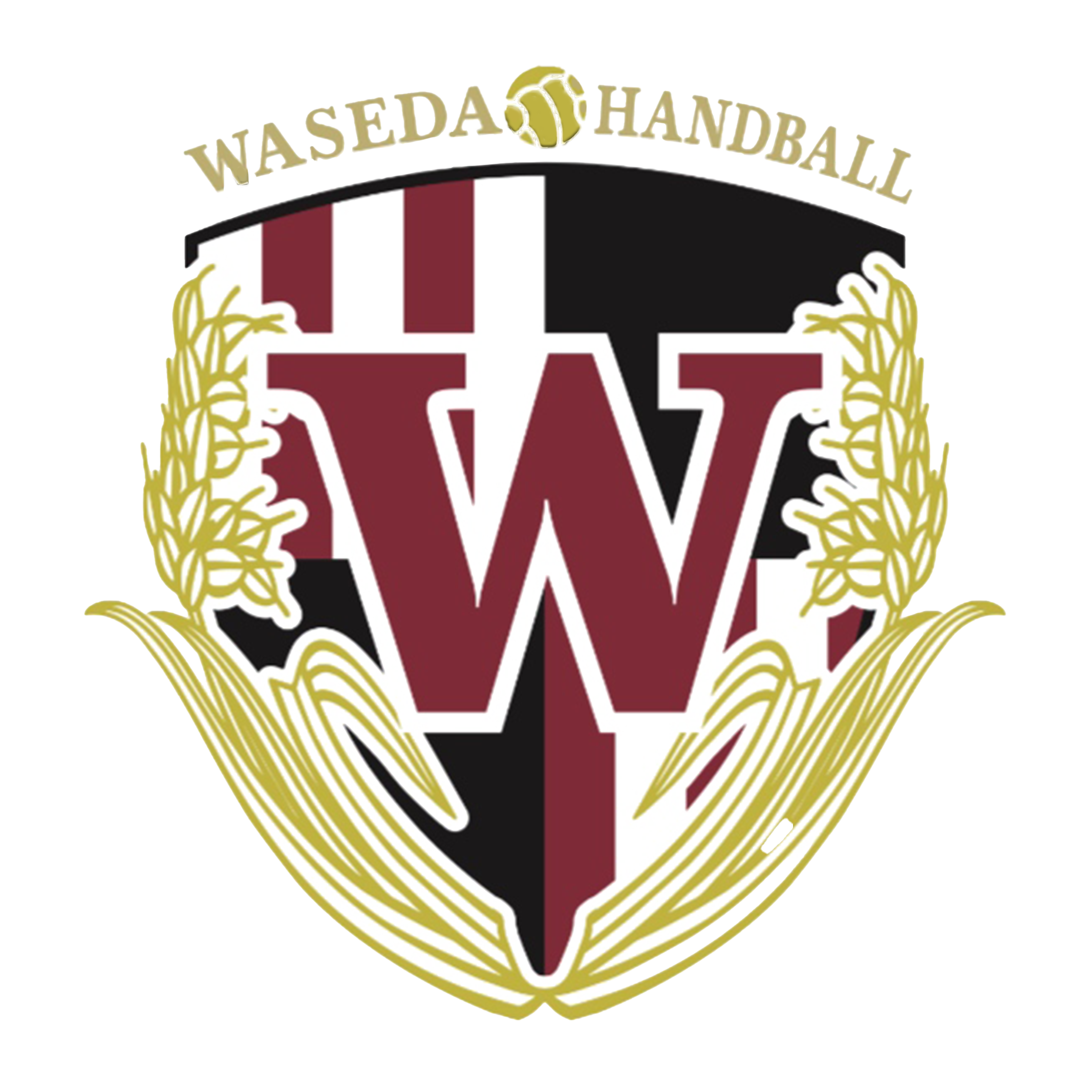12月2日(土)に早稲田アリーナにて開催する男子第71回・女子第20回早慶ハンドボール定期戦およびOB・OG戦の事前申し込み方法、グッズ販売についてご案内をいたします。
今年は4年ぶりにOB・OG戦が開催されます。ご都合のよろしい方は、是非会場までお越しください。
【日時】2023年12月2日(土)
於 早稲田アリーナ(東京都新宿区戸山1丁目24−1)https://maps.app.goo.gl/Hm2ongZvorZ5myhq8?g_st=ic
【タイムスケジュール】
10:30 開場
11:30 OG戦(20分ハーフ)
12:40 OB戦開始(20分ハーフ)
13:50 開会式
14:20 女子現役戦開始
16:05 男子現役戦開始
17:40 閉会式
19:00 レセプション開始
20:30 レセプション終了
【観戦申込(保護者・一般)について】
入場料は無料ですが、事前申し込みが必要です。こちらのフォームからお申し込みください。
https://forms.gle/LmgxYREm8wLyp5m16
【観戦申込(OBOG)・OBOG戦参加について】
今年度は、4年ぶりにOB・OG戦を開催いたします。観戦のみでも構いませんので、ご都合のよろしい方は、是非ご来場ください。OB・OG戦参加及び観戦、現役戦観戦のお申し込みは、以下フォームよりのお願いいたします。
https://forms.gle/A3S5CiDhSK3rzPs99
【グッズについて】
記念Tシャツの販売は、申し込みフォームを通じて行います。当日、会場にて販売も行いますが、数に限りがあるため、フォームを通じての事前申し込みをお願いします。その他、サイズやデザイン、受け取り方法等の詳細は、以下のURLよりご確認ください。
https://forms.gle/r92KxMKeR9D5upfG6
【最新情報】
早慶戦公式Instagramにて最新情報を更新しています。こちらよりアクセスお願いします!